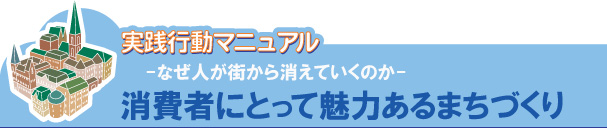II-3.実現可能な戦略の構築
地域の特性を理解しないまま、
無理な戦略の構築をしていませんか?
~特性の違いを知ることで、適切な方向を見いだします~
![]() コンセプトに沿った実施可能な戦略を探る
コンセプトに沿った実施可能な戦略を探る
●中心市街地ならではの特性や注意点とは何か?
- 商業集積と郊外型ショッピングセンター(SC)との違いは何かわかりますか?
- 真似できないところとできるところを見極める。
- 商業集積とSCのそれぞれの特性を比較検討してみる。
【中心市街地と郊外型SCとの特性比較】
| 中心市街地 | 強化策 | 郊外型ショッピングセンター | ||
| 起源 |
・自然発生的
・個性的 |
・個性の回復
・界隈性の回復 ・街づくりの視点重視 |
・計画発生的
・均質的(どのSCも似ている) |
|
|
テナントミックス
(空き店舗含) |
・地元店舗中心
・自然で不作為な構成 ・コントロールが難しい |
・既存店強化
・地域有力店中心のテナントミックス |
・ナショナルチェーン中心
・人工的に計画された構成 ・全体的にコントロールできる |
|
| 経営状況把握 |
・把握が難しい
・業績の変化が把握しにくいため、問題意識に上りにくい |
・売上の把握 |
・各テナントの売上を把握
・業績の変化が賃料等に即時に反映するシステム(歩率賃料)が多い |
|
| 商圏 |
・地域商圏の重要性が高いことが多い
・平日集客中心 |
・地域商圏の見直し |
・広域型商圏
・土日集客中心 |
|
| 運営 |
・一体的な運営は難しい
・組織の体系化が困難 |
・TMOの活用 |
・一体的な運営を行う
・運営組織が体系化、規格化されている |
|
|
付加
価値 |
・計画的に都市型機能やアミューズメント機能等の導入は難しい。
・公共・教育、福祉、生活サービス等の立地妥当性は高い ・観光要素など、他の要素の影響(恩恵)を受けやすい ・その他の無形資産(歴史、物産等)の存在 |
・地域活性化計画の再構築
・新たな集客機能導入の可能性を幅広く検討 ・地域の無形資産(資源)の活用可能性の検討 |
・知名度が高い
・計画的にシネマコンプレックス、アミューズメント、スポーツ、温浴等、非商業機能も導入 ・大型付帯施設が多く、付帯施設の集客力も強い ・テレビCMなど大掛かりな販促が可能 ・観光要素など他の要素の影響(恩恵)を受けにくい ・均質的な性格のため、その他の無形資産の活用があまり有効でない |
● 調査の目的
- 商業地の特性をつかんで、身の丈にあった方向性を設定する
- 特性に見合った商圏の見直しを行う
- 途中で迷った時などに、指標となる基本コンセプトや基本戦略の確認を行う
●商業強化の基本的方向性(戦略)の確認
基本的方向性(戦略)は「商圏の拡大化」と「商圏の深耕化」の2つに集約されます。具体的な方策を考え、その実現性を検討しながら、どちらの方向性が適しているかを確認します。
【商圏の拡大化と深耕化の考え方】
| 戦略の基本的方向性 | 具体的な方策例 | |
|
商圏の 拡大化 |
現状の商圏より、広いエリアからの集客を図っていく戦略であり、買い回り品を中心とした店舗の構成や、観光要素を活用した商業等が考えられる
|
・観光資源を活用して広域から集客
・飲食等特徴的な集積の形成によって商圏を拡大 ・ファッションに特化した商業集積を形成して商圏を拡大 |
|
商圏の 深耕化 |
商圏を広げるのではなくむしろ絞り込んで、地域に密着したニーズに応える。比較的近いエリアからお客さまに足繁く通って頂き、かつ繰り返し購買して頂く戦略、日常性の高い最寄り品が中心となる
|
・日常的な食料品の充実によって、地域からの支持を得る
・利便性の向上を図り、近隣からの支持を得る ・コミュニティやサービスの充実を図り、地域からの支持を得る |
●テナントミックスに係わる事業
|
1 既存集積・ 店舗強化 (業態転換) |
2 空き店舗対策 新機能導入 |
3
共同店舗 |
- 基本コンセプトや基本戦略をふまえ、それぞれの計画を進めていきます。
- 一般生活者・消費者の視点に立って、発想することが大切です。
![]()
- 商圏の拡大化と深耕化の意味が理解できましたか? それぞれの具体策は何ですか?
- テナントミックスに係わる3つの基本手法のイメージがわきますか? 具体的な方法は何がありますか?
- 調査結果等を再確認する
- 方向性を設定する時に、もう一度「商圏」と「消費者ニーズ」の点検を行う。
- お客様の視点が入っているか再度確認する。