3.1.1.3 目標復旧時間を決める
(1) 実施のポイント
災害時における中核事業復旧の遅れは、その分だけ、事業機会の損失を被っているということになります。事業復旧が大きく遅れると、最悪の場合、主要な顧客との取引解消にもつながるため、結果として会社の存続が危ぶまれることは想像に難くありません。そこで事業中断による被害を極力小さく抑えるためには、中核事業を復旧させるまでの期限の目安となる目標復旧時間†2を決める必要があります。
目標復旧時間を決めるにあたっては、最低限、以下の2つを考慮する必要があります。
①中核事業に関わる取引先やサプライチェーンの要請
②あなたの会社の財務状況にもとづく時間
まず①については、中核事業の特定により、それに関連する取引先やサプライチェーンに含まれる会社が把握できますので、あなたの会社が被災した場合に、それらの取引先から許容される事業停止時間の限度を把握しなければなりません。これは、取引先の経営者や幹部従業員との直接的なコミュニケーション等を通して把握・調整しておくべき事項です。
一方、②については、特定した中核事業の停止による損失に対して、あなたの会社の資金が耐えられる限界の期間を見積もっておく必要があります。具体的には、中核事業が停止した場合の収入の途絶に加えて、納期遅延等による違約金、その間の従業員の賃金、災害対応のための臨時人員の賃金、事業所や設備機器が被災した場合の修繕や新規調達費用等が発生しますので、それらの費用負担に対して、どれだけの期間耐えられる資金があなたの会社にあるかを見極めなければなりません。
以上の2点を十分に加味した上で、目標復旧時間を設定して下さい。
ただし、①について、被災の程度や理由により、取引先からの許容の度合いが変化することも考えられます。例えば、広域的な自然災害によって道路やライフライン等が甚大な被害を受けたため、周辺地域の人命救助を優先するため†3等、事業の早期復旧に着手できない場合には、取引先からの許容の度合いが変わることがあります。
そのため、目標復旧時間を設定した上で、万が一実際に被災してしまった際には、被災の規模や状況により、取引先に対して、目標設定時間よりも事業復旧が遅れることに関する理解を求めることが必要になるでしょう。
なお、過去の災害時における被災企業の目標復旧時間の設定事例がありますので、業種や被災状況に留意した上で参考にしながら、目標復旧時間を設定して下さい。
(目標復旧時間を検討する際には、資料05、資料06、資料07が参考にできます。)
【BCP帳票への記入】
・ ここまでの検討結果を整理するために、”〔様式06〕中核事業に係る情報” が利用できます。
・ ここに整理される情報はあくまで基本的な情報ですので、その他に必要な情報は、備考欄を活用するなどして、参照しやすいように整理して下さい。



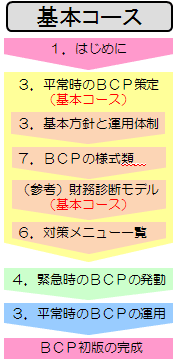
 公開にあたって
公開にあたって



