3.1.2 中核事業が受ける被害を評価する
(1) このステップの目的
このステップの目的は、あなたの会社の中核事業が受ける可能性がある被害にはどのようなものがあるかを把握し、被害の大きさを評価することです。これにより、中核事業を被害から守るための取組みを検討することが可能となります。
(2) 実施のポイント
このステップでは、前のステップで決定したあなたの会社の中核事業が受ける被害の程度を評価します。その際、以下の手順により評価することができます。
① 中核事業が影響を受ける可能性が高いと思われる災害を想定する
一般的に企業が影響を受ける災害には、地震、風水害、火災、鳥インフルエンザのような感染症等、様々なものがあります。理想的には、あらゆる災害に対して中核事業が受ける影響を評価するべきですが、現実的には容易ではありません。そのため、いくつかの代表的な災害を想定して、中核事業の被害を評価することが望ましいでしょう。ただしその際、災害として想定する規模(地震であれば震度)も同時に想定しておくようにして下さい。この規模の設定について、どれくらいが妥当かという基準は一般的にはなく、企業ごとに異なるものですので、経営者による意思確認は重要となります。
(災害を検討する際には、資料03が参考にできます。)
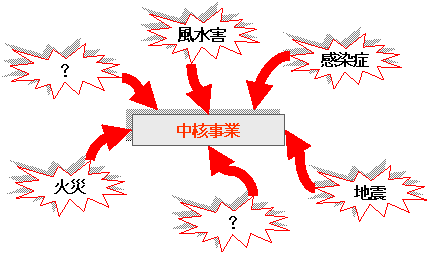
図 中核事業に影響を及ぼす様々な影響
② 想定した各災害が中核事業のボトルネック資源に与える影響を評価する
ここでは、前のステップで把握したボトルネック資源(事業継続のための障害となる資源)を利用します。
「ほぼ操業できなくなる」または「人手による代替等で、一部は操業できる」と評価した各ボトルネック資源に対して、想定している災害が与える影響をそれぞれ考えて下さい。なお、ここでは、「重要業務」におけるボトルネック資源は、同時に「中核事業」のボトルネック資源であることを前提とします。
この時、影響の度合いの目安として、次の1)~3)に示す3段階で判断してもよいでしょう。また、影響度が判断できない場合は、高めの影響として想定しておくほうが、中核事業の継続検討において確実性をもたせるものになるでしょう。
- 1)
- 想定した災害により、 ボトルネック 資源は、 目標復旧時間 内の復旧に間に合わない程度の量の影響を受ける、または、 目標復旧時間 内の復旧に間に合わない程度の時間、影響を受け続けると考えられる
- 2)
- 想定した災害により、 ボトルネック 資源は、ある程度の量/時間は影響を受けるが、 目標復旧時間 内の復旧には間に合うと考えられる
- 3)
- 想定した災害からはほとんど被害を受けないと考えられる
例として、「電力」がなくなると、中核事業が「ほぼ操業できなくなる」と、あなたが評価したとしましょう。
そして、想定している災害の一つが「震度6強の地震」である場合、それにより「電力」が受ける影響はどの程度かを考えてみて下さい。これは具体的には、あなたの会社付近で震度6強の地震が発生した場合、何時間または何日間程度、電力の供給が停止するかという質問に置き換えることができます。
この時仮に、ボトルネック資源である「電力」への影響が、上の選択肢1)のように、中核事業の目標復旧時間に間に合わない程度であるとすると、結果として「震度6強の地震により電力が被害を受けると、中核事業を目標復旧時間内に復旧することはできない」という結論が導かれます。
このような分析を中核事業に必要なすべてのボトルネック資源について行って下さい。そうすることにより、ここで想定している災害が各ボトルネックに与える影響を把握できます。
(災害が資源に与える影響を検討する際には、資料03、資料04が参考にできます。)
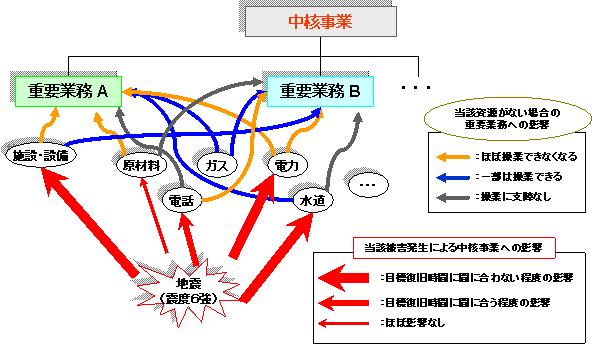
図 地震(震度6強)が中核事業に与える影響のイメージ
次の表の1~3に該当するボトルネック資源は、中核事業の復旧を大きく左右する要素といえるものです。特に1に該当するボトルネックが多いほど、想定した災害が中核事業に与える影響が大きいということになります。
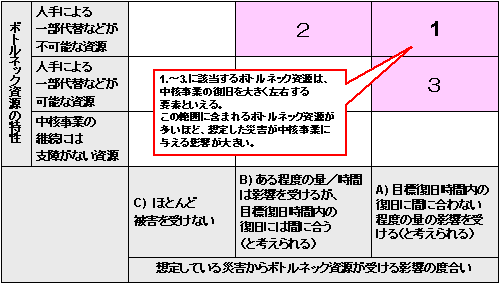
図 ボトルネック資源が中核事業の復旧に与える影響度
以上の手順により、ある一つの災害がボトルネックを通して中核事業に与える影響の全体を把握することができますが、引き続き、他の災害についても同様の手順を実施することが望まれます。
このような分析はそれ相応の時間を要しますが、大事なことは、「どのような災害によってボトルネックがどの程度の影響を受け、中核事業の継続にどの程度の支障をきたすのか?」を漏れなく把握することです。したがって、経営者の判断により、災害の種類・規模と、中核事業への影響の大きさを対応づけて設定し、以降のステップに進むことも許可されます。その場合、影響度の妥当性は継続的なBCPの運用において改善すればよいでしょう。
また、上述した影響度の評価を実施するために、〔様式07〕の「中核事業影響度評価フォーム」を用意していますので、より体系的に分析してみたい場合には、こちらを利用することも推奨されます。



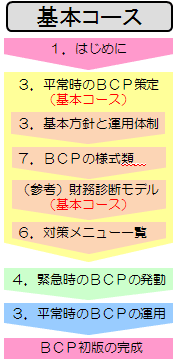
 公開にあたって
公開にあたって



