5.4 事前対策の考え方
事前の対策をする場合は、資金調達の形が下表のように変わります。対策費用を自己資金で行うか、資金を借り入れるかで、別途の検討が必要になります。
事前の対策を自己資金で毎期着実に実行していくことが望ましいのですが、緊急に対策を講ずる必要がある場合には、災害防止対策資金の借入を検討することが必要になります。
表 事前対策検討表
(単位:千円)
|
必要資金の金額 |
調達可能金額 |
備 考 |
|||
|
(災害防止対策費用)(F) |
手許現金・預金 |
|
|||
|
(復旧資金) |
|||||
|
経営者から支援 |
|||||
|
災害防止対策資金借入金額(G) |
|||||
|
災害時新規借入金額(E) |
|||||
|
計(F)+(C)=(H) |
計 |
|
|||
事前に対策を講じておけば、災害時の「設備の復旧費用+事業中断によるキヤッシュフローの悪化額」即ち「復旧費用総額」は間違いなく減少します。このことを、計数で表すことは難しいのですが、下記はその概念図です。
ケース1 ケース2 ケース3
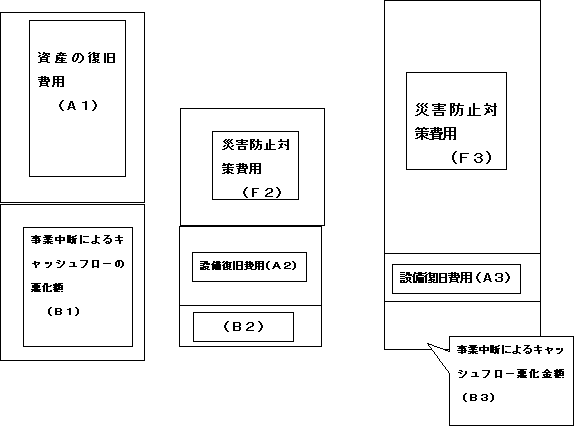
(A1)+(B1)=(C1) (A2)+(B2)=(C2) (A3)+(B3)=(C3)
(F2)+(C2)=(H2) (F3)+(C3)=(H3)
前対策なし 有効な事前対策あり 過度の事前対策を実施
図 事前対策費用の効果概念図
事前に何も防災対策を講じていない場合の復旧資金総額(C1)より、有効な事前防災対策を講じた場合の必要資金総額(H2)は少なくなる筈です。
理論的には事前の防災対策を全く行わない場合の復旧費用(A1+B1=C1)が、事前対策を講じた場合の総費用(A2+B2+F2=H2)より大きい場合 C1>H2であれば、事前防災対策を講じるべきです。(概念図参照)
企業としての費用負担総額は、上記のケース(2)、(3)の図のように累計で考えなければなりません。
過度の災害防止対策を実施した結果、災害防止対策を何も行わなかった場合より企業の累計負担額が大きくなる ケース(3) (A1+B1=C1)<(A3+B3+F3=H3) =C1<H3も考えられます。これは行き過ぎです。
本表を生かすためには、更に細かく検討をしなければなりません。これについては、上級コースで検討します。
事前防災対策を借入で賄う場合は、返済原資・担保条件の検討が必要になります。事前対策は、貴方の会社自身で調達できる金額の範囲で、先ず行いましょう。事前対策については、【VI.事前対策メニュー】を参考とし、なお貴方の会社の資金調達を考慮して考えましょう。
【付録】用語の記号
資産の復旧費用 (A)
事業中断によるキャッシュフローの悪化額 (B)
復旧費用総額 (C)
手元資金 (D1) 自力で賄う場合
調達可能金額 (D2) 借入を要する場合
新規借入金額 (E)
新規借入可能金額 (e)
災害防止対策費用 (F)
災害防止対策資金借入金額 (G)
災害対策の必要資金総額(事前対策費用を含む) (H)



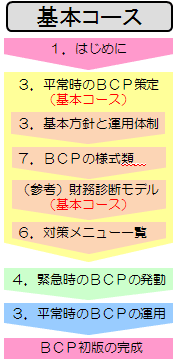
 公開にあたって
公開にあたって



