3.1 事業を理解する
(1) このプロセスの目的
企業においては、大小様々な事業と、それに関わるいくつかの業務がありますが、大災害や大事故の発生時には、限りある人員や資機材の範囲内で、あなたの会社の事業を継続させていかなければなりません。そのため、まずどの商品を優先的につくるか、どのサービスを優先的に提供するかという経営判断を予め行っておくことが、BCPの第一歩となります。
(2) このプロセスでの実施内容
① 事業への影響度を評価する
まずは、あなたの会社の中核事業を特定します。「中核事業」とは、本指針では「会社の存続に関わる最も重要性(または緊急性)の高い事業」を示します。中核事業は最終的には経営者の判断によって決定されるものであり、あなたの会社において重要と思われる事業をいくつかあげて、その中で財務面、顧客関係面、社会的要求面から、優先順位を付けていくことが望ましいでしょう。
検討事項①:あなたの会社の中核事業は何ですか?
(例:顧客"甲"に対する製品"A"の製造・提供)
なお、中核事業として、複数の顧客に対して同一の製品"A"の提供を設定する場合には、「顧客"甲"、"乙"、・・・に対する製品"A"の製造・提供」となりますし、特定の顧客"甲"との契約履行が最優先であり複数の製品提供が求められる場合には、「顧客"甲"に対する製品"A"、"B"、・・・の製造・提供」となります。
中核事業を特定したら、次は、受注、部材在庫管理、出荷、配送、支払い、決済といった、中核事業に付随する業務を把握します。本指針では、この業務のことを「重要業務」と呼びます。
検討事項②:あなたの会社の中核事業及び重要業務を継続するために必要な資源(人、物、金、情報等)には何がありますか?
(可能な限り漏れが無いように、思い付く限りあげて下さい。)
本指針では、これらの資源を「ボトルネック資源」と呼んでおり、中核事業、重要業務、資源の関係は、下図のようになります。例えば「人」には、あなたの会社の従業員や協力会社が含まれますし、「物」には、施設や設備、原材料、電力・ガス・水道といったインフラも含まれます。
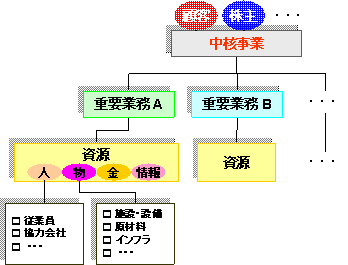
図 中核事業、重要業務、資源の関係
また、中核事業を復旧させるまでの期限の目安となる目標復旧時間も決めておきます。目標復旧時間を決めるにあたっては、「中核事業に関わる取引先と事前に調整して決める」、もしくは、「中核事業の停止による収入途絶等の損害に、あなたの会社が耐えられる期間にもとづいて決める」の2つを考慮して決定するのがよいでしょう。
検討事項③:あなたの会社の中核事業の目標復旧時間はどの程度ですか?
(目標復旧時間を検討する際には、資料05、資料06、資料07が参考にできます。)
② 中核事業が受ける被害を評価する
あなたの会社の中核事業が、地震、風水害、火災等の災害によりどの程度の影響を受けるのかを評価します。そのためには、前のステップで把握した中核事業の継続に必要な資源が、どのような災害によって、どの程度の影響を受け、中核事業の継続にどの程度の支障をきたすのかを、可能な限り漏れなく把握することが望まれます。
検討事項④:中核事業が影響を受けると思われる災害には何がありますか?
(災害を検討する際には、資料03が参考にできます。)
検討事項⑤:④で想定した各災害が、中核事業の継続に必要な資源のそれぞれに与える影響を把握して下さい。
(災害が資源に与える影響を検討する際には、資料03、資料04が参考にできます。)
この際、中核事業が影響を受ける災害それぞれについて、中核事業の継続に必要な資源を、「目標復旧時間内に機能回復しないもの(回復させられないもの)」または「目標復旧時間内に機能回復するもの(させられるもの)」のどちらかに区別しておくことが望ましいでしょう。なぜなら、「目標復旧時間内に機能回復しないもの(回復させられないもの)」であれば、その資源については、代替となる資源をどのように確保するかを検討することになり、一方、「目標復旧時間内に機能回復するもの(させられるもの)」については、その資源をどのように機能回復させるか、または、その資源の機能が回復するまでの時間をどのように対応したらよいかに関する検討につなげるためです。
上述した影響度の評価を実施するために、〔様式07〕の「中核事業影響度評価フォーム」を利用して、より体系的に分析することも推奨されます。
③ 財務状況を分析する
あなたの会社が地震等により被災した場合、建物・設備の復旧費用や事業中断による損失を具体的に概算しておいて下さい。その状況によっては、被害を軽減するための以下のような事前対策を採るべきかどうかの判断をしておいて下さい。
【5.財務診断モデル(基本コース)へ】
・適切な損害保険の加入
・事前の対策実施 等
災害発生後、多くの中小企業で復旧資金の借入が必要になるものと考えられます。このBCPを実行することによって、災害発生後の政府系中小企業金融機関・保証協会等の災害復旧貸付・保証制度をより有効に活用できます。
(被災中小企業に対する公的支援制度については、資料10が参考にできます。)
【BCP帳票への記入】
・ここまでの検討結果を整理するために、"〔様式06〕中核事業に係る情報"が利用できます。
・ここに整理される情報はあくまで基本的な情報ですので、その他に必要な情報は、備考欄を活用する等して、参照しやすいように整理して下さい。



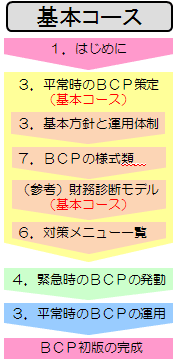
 公開にあたって
公開にあたって



