3. 平常時におけるBCPの策定と運用(基本コース)
ここでは「基本コース」として、中小企業にとって最低限必要とされるBCPを、「できるだけ早く」、そして「できるだけ簡単に」つくるための策定手順について、解説していきます。しかしその前に、「なぜ、BCPを策定する必要があるのか?」について、改めて確認しておきましょう。
例えば、あなたの会社が以下のような状況に陥った場合、あなたの会社は、通常通りの業務を本当に継続できるかどうか、考えてみて下さい。
- 例1.
- 大規模地震の発生により、あなたの会社の事務所にあるパソコン等の機器類の多くが机から落ちたり、あなたの会社の工場にある重要な生産設備が転倒したりして、使用できなくなった場合
- 例2.
- 火災の発生により、あなたの会社建屋をはじめとして、事務所にある各種の書類やパソコン等の機器類、あなたの会社の工場にある重要な生産設備等が焼失して、使用できなくなった場合
- 例3.
- 近所の河川の大氾濫により、あなたの会社事務所や工場が浸水して、事務所での業務が不可能になったり、工場にある重要な生産設備が使用できなくなったりした場合
- 例4.
- インフルエンザや新型 感染症 の大流行により、あなたの会社の従業員の大半が、1週間以上出社できなくなった場合
大抵の場合、事前に何も準備や心がけをしていなかった会社が上のような状況に陥ってしまうと、通常通りに操業し続けることは非常に困難になることが予想されます。
特に中小企業の場合は、このような原因による操業停止が廃業や倒産に直結する可能性が高いことから、突発的に発生するこのような緊急事態に対して平常時からの準備が必要となることを、まずはあなた自身の喫緊の課題として意識することが重要です。また、大企業のサプライチェーンに属する中小部品メーカーの場合には、サプライチェーン全体に重大な影響を与える場合もあり、その影響は被災地に止まらず日本全国に波及する場合もあります。
このような理由から、あなたの会社が自然災害や火災等の緊急事態に遭遇した場合において、事業に不可欠な資産への損害を最小限に止めつつ、中核となる事業の継続や早期復旧を実現するために、平常時から行うべき活動と緊急時における事業継続のための方法、手段等を事前に取り決めておくことが必要となるのです。この計画こそが、これから策定するBCP(事業継続計画)です。
BCPを準備しておくことは、緊急時における事業の継続・早期復旧を実現させるだけでなく、顧客からの信用の維持や、市場関係者や株主からの評価の向上につながります。
具体例をあげますと、以前は、特に大規模災害により被災した会社の事業中断等に対しては、取引先企業からの温情等により、ある程度の免責的な措置が採られることが少なくありませんでした。
しかし、グローバル化の進展の中で、事業の競争環境が一層厳しくなっていくと、「緊急事態発生時だから、事業中断は仕方がない」では通用しなくなることも十分に考えられるのです。もしあなたが取引先企業の担当者であれば、他の条件がほとんど変わらない場合、BCPを策定しているA社とBCPを策定していないB社のどちらの会社と契約したいと考えるかは明らかでしょう。
以上のような様々な背景のもとに、あなたの会社においてもBCP策定が必要なのであり、かつ、社会からも期待されているのです。
基本コースでは、主に経営者ご自身の主観で「7. BCPの様式類」にある各様式に記入することで、BCPの策定までを行います。記入したシートの内容は、全従業員と共有し、緊急事態に備えることが望まれます。
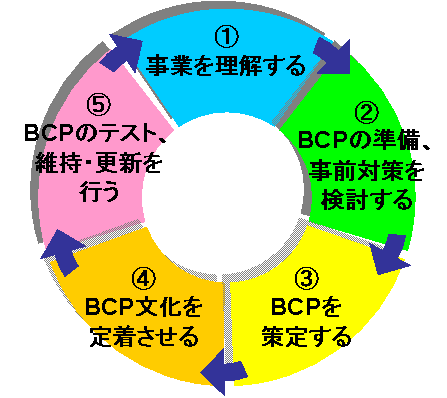
図 BCPの策定・運用サイクル



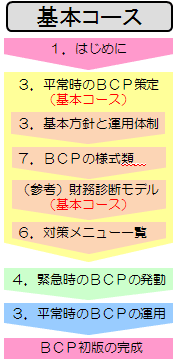
 公開にあたって
公開にあたって



