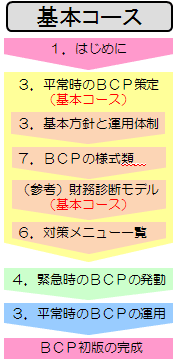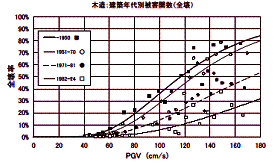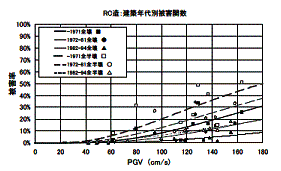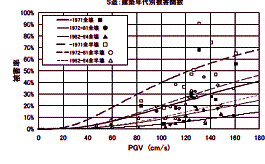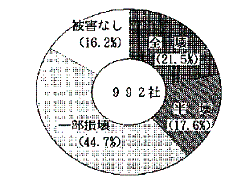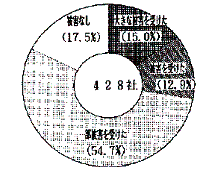資料16 財務診断モデルにおける緊急時被害想定方法
○建物被害
建物被害については、次の通り設定している。
・揺れによる被害
震度・建物構造・建築年代に応じた建物の全壊率、半壊率は村尾・山崎による式(2000)を用いた被害率を利用することとする。これは阪神・淡路大震災の事例をもとにしたものである。全壊、半壊の定義は次の通り。
表 阪神・淡路大震災時の自治体による全壊・半壊の定義
|
被災度 |
判定基準 |
|
全壊 |
住家が滅失したもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要構造物の被害額がその住家の時価50%以上に達した程度のもの |
|
半壊 |
住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。具体的には損壊部分が住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価20%以上50%未満のもの |
村尾・山崎式(2000)(左側)は次のような被害率曲線を描く。(図は、村尾・山崎「震災復興都市づくり特別委員会調査データに構造・建築年を付加した 兵庫県南部地震の建物被害関数」、日本建築学会構造系論文集,第555号,185-192,2002年5月より)
|
○木造 |
○鉄筋コンクリート(RC)造 |
|
|
|
|
○鉄骨(S)造 |
|
|
|
そして、財産上の被害が50%~100%の場合を全壊、20%~50%場合を半壊ということから、それぞれ中間値をとって、(0.75×全壊率+0.35×半壊率)を建物の資産額に掛け合わせたものを地震による建物被害額としている。
・床上浸水
床上浸水が生じた場合の家屋の被害率について、国土交通省による東海豪雨における被害率である評価額の0.231倍を利用し、0.231倍を建物の資産額に掛け合わせることとしている。
・全焼
火災の場合も全壊と同様、財産上の被害が50%~100%を全焼としているので、その中間地をとって0.5を建物の資産額に掛け合わせることとしている。
○建物附属設備
建物附属設備については、建物と同様の計算方法により被害額を算出している。
○機械及び装置
・地震
機械及び装置については様々なものが考えられるが、それら個別の被害を設定するのは困難であるため、地震事例をもとに一般的な被害額の評価を行うこととした。地震の場合の機械及び装置の被害状況については、社屋の被害との関係で、次のようなグラフが得られている。(「阪神大震災に関する被害及び今後の神戸経済に関する調査結果」、神戸商工会議所)
|
|
|
ここで、建物については、全壊→75%の被害、半壊→35%の被害、一部損壊→10%の被害と考え、一方機械・設備については大きな被害を受けた→75%の被害、被害を受けた→35%の被害、一部被害を受けた→10%の被害として、上記のグラフを使って建物、機械・設備の平均的な被害を出すと、建物については26.8%、機械・設備については21.2%であるから、この比率をとって、機械及び装置の資産額×建物の被害率×21.2%/26.8%を機械及び装置の被害額とした。
・床上浸水
床上浸水の場合の被害額については、国土交通省による東海豪雨の調査結果における償却資産の被害率0.498を機械及び装置の資産額に掛け合わせた値とした。
・火災
火災の場合の被害額については、建物の場合と同様、機械及び装置の資産額の75%とした。