資料02 関連指針との比較
本指針は、基本的に内閣府のガイドラインと整合性を持つものですが、①中小企業向けであることから事業継続に関する各種ノウハウ(財務診断モデルや事前対策メニューなど)を数多く記載していること、②BCP(事業継続計画)に関する専門用語をなるべく平易な表現としていることなどに特徴があります。以下に両者の比較表を示します。
|
内閣府「事業継続ガイドライン」 |
中小企業庁「中小企業のための |
備考 |
|
【ポイント】 |
1.1 BCP(事業継続計画)とは |
○本指針でもBCPの特徴を説明。 |
|
Ⅰ 事業継続の必要性と基本的考え方 |
|
|
|
1.1 事業継続の必要性とポイント |
1.1 BCP(事業継続計画)とは |
○本指針でもBCPの必要性を説明。また、中小企業がBCPに取り組む際のポイントを記載。 |
|
1.2 基本的考え方 |
1.1 BCP(事業継続計画)とは |
○内閣府ガイドラインは地震災害が対象、本指針は地震災害を含む全ての緊急事態を対象としている。 |
|
1.3 継続的改善 |
3.4 BCPの診断、維持・更新 |
○本指針3.4節で、BCPの維持・更新の必要性について言及。 |
|
Ⅱ 事業継続計画および取組みの内容 |
|
|
|
2.1 方針 |
2.1 基本方針の立案 |
○両者ともに、事業継続の基本方針を立案・周知すること、体制と資金の確保が必要なことを記載。 |
|
2.2 計画 |
1.1 BCP(事業継続計画)とは |
○内閣府ガイドラインは地震災害が対象、本指針は地震災害を含む全ての緊急事態を対象としている。 |
|
2.2.2 影響度の評価 |
3.1 事業の理解 |
○本指針3.1節で、BCPサイクルに沿って同様の内容を説明。ただし、中核事業と重要業務の用語を使い分けている。 |
|
2.2.5 事業継続計画の策定 |
3.2 BCPの準備、事前対策の検討 |
○本指針3.2節で、中核事業に関わる代替策の検討と事前対策の実施を説明。 |
|
2.2.6 事業継続と共に求められるもの |
2.1 基本方針の立案 |
○本指針2.1節で、企業同士の助け合い、地域貢献の重要性を説明。 |
|
2.3 実施および運用 |
3. 平常時におけるBCPの策定と運用 |
○本指針では、平常時にBCPサイクルを回すことが重要であることを説明。 |
|
2.3.2 文書の作成 |
3.3 BCPの策定 |
○本指針3.3節で、BCPの様式類に記入することで緊急時事業継続活動の参照データベースを得る。また、BCP策定・運用の図上テストに用いるチェックリストを3.6節に用意。 |
|
2.3.3 財務手当て |
5.財務診断モデル |
○本指針は、中小企業向けであり、財務措置が特に重要になると考え、経営者が自己診断できるモデルを用意した。 |
|
2.3.4 計画が本当に機能するかの確認 |
3.5 BCPの診断、維持・更新 |
○本指針3.5節で、BCPの診断について言及。また、図上診断に用いるチェックリストを3.6節に用意。 |
|
2.3.5 災害時の経営判断の重要性 |
4. 緊急時におけるBCPの発動 |
○本指針4章の冒頭で、エスカレーションの考え方を説明。 |
|
2.4 教育・訓練の実施 |
3.4 BCP文化の定着 |
○本指針3.4節で、教育・訓練のほか文化醸成について言及。 |
|
2.5 点検および是正措置 |
3.5 BCPの診断、維持・更新 |
○本指針3.5節で、BCPの維持・更新について言及。 |
|
2.6 経営層による見直し |
3.5 BCPの診断、維持・更新 |
○本指針3.5節で、BCPの維持・更新について言及。 |
|
Ⅲ 経営者および経済社会への提言 |
(該当なし) |
|



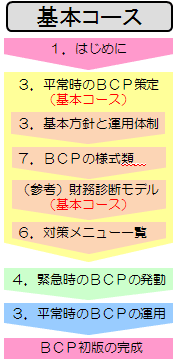
 公開にあたって
公開にあたって



