(1)地震
東海地震には警戒宣言(地震予知に基づく事前対応)がありますが、その他の地震では突発的に地震が発生することから、突発地震を想定して初動対応を整理しました。また、警戒宣言が発令された場合には、強化地域内では企業活動は原則として停止するため、地震が発生した場合でも被害が減少し、以下に示す初動対応の範囲内で対応することが可能と考えられます。
【ポイント1】発災直後の安全確保
発災直後は、自分の身の安全の確保が必要です。落下物に気を付けつつ、大きな什器等から離れて机の下等に隠れて様子を見守りましょう。
【ポイント2】津波からの避難
津波の危険性がある場合には、早急に高台等の指定避難場所に避難することが必要です。特に津波の危険性が指摘されている地域では、大きな揺れを感じたら素早く避難を開始することが求められます。津波は第2波や第3波が最大波高となる場合が多く、一旦津波が引いた場合でも沿岸部や浸水地域には近づかないようにしましょう。
【ポイント3】2つの安全確認
安全な場所に避難するかどうかは、建物の被災状況と共に、土砂災害や堤防決壊等による影響も踏まえて判断するようにしましょう。
【ポイント4】各自がルールに従い行動すること
発災直後は混乱していて社長が自ら全ての指示を出すことは困難であり、従業員が自発的に行動できるように、初動の活動や役割を従業員に周知しておきましょう。
【ポイント5】会社以外の場所にいる場合の対応
地震が発生した場合に必ずしも会社にいるとは限りません。在宅時や通勤中、就業時間内の外出中の場合も考えられます。いずれの場合も会社への連絡は必要ですが、出社すべきかどうか等のそれ以外の事項については、どのような対応をとるべきかを予め決めておくことが必要です。従業員に携帯カードを配布する場合には、携帯カードにいくつかの場合ごとの対応について書いておくとよいでしょう。
【ポイント6】他の地域の状況も確認すること
自分達が被災しない場合でも、他の地域で大きな被害が発生して取引先が被災した場合には間接的な影響が予想されるため、他の地域の状況も確認しましょう。
また、地域に対しては要請を待つのではなく、積極的に支援ニーズが無いか確認する姿勢が大切です。そのため、緊急に帰宅する必要性の低い従業員は、地域への支援に積極的に参加することが求められます。
【注意】「揺れの大きさ」「建物の安全確認」
気象庁の震度階級関連解説表にもあるとおり、主に震度6弱以上で建物被害が発生し震度5強以下では建物被害は軽微と言われています。ただし、昭和56年に改正された建築基準法より以前に建設された古い建物のうち耐震性が低いものについては、重大な被害が発生する可能性もあるので(特に木造建物は耐震性が低い)、震度5強以下の場合でも、危険と思われる場合には建物内部に留まらずに外部に避難することが必要です。
※ 震度階級関連解説表
http://www.kishou.go.jp/know/shindo/kaisetsu.html
【参考】
気象庁(地震情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
気象庁(津波情報)
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
気象庁(東海地震関連情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake_tokai/
防災科学技術研究所(高感度地震観測網)
http://www.hinet.bosai.go.jp/
表 地震時の状況イメージ
|
場所 |
状況イメージ |
|
オフィス 店舗 |
・ オフィス家具等が転倒する。ガラスが散乱する。 |
|
周辺 |
・ 建物の変形や倒壊等の被害が発生する。 |
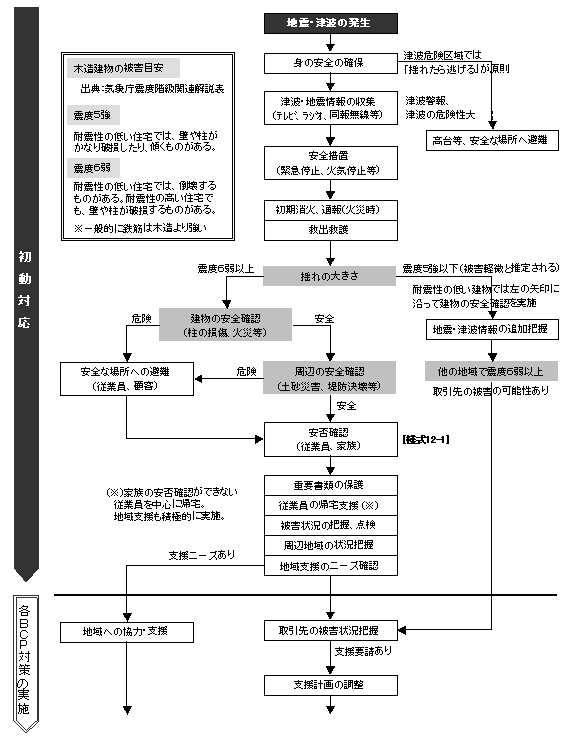
図 初動対応フロー(地震)



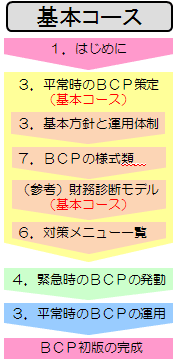
 公開にあたって
公開にあたって



