(2)事業継続のための緊急対策
初動対応が済んだら、経営者がリーダーシップをとり、従業員に事業継続のための緊急対策を指示します。
できる限り速やかに顧客・協力会社と連絡を取ります。安否・被害状況の把握結果を踏まえ、中核事業の継続方針を立案し、その実施体制を確立します。
①顧客・協力会社への連絡
お客さま及び協力会社との連絡手段を確保し、被災状況等について相互に報告します。
|
顧客・協力会社への連絡 |
||
|
●連絡手段の確保 |
・顧客や協力会社との連絡手段を確保する。 |
|
|
●顧客への被災状況報告 |
・顧客に対して、事業所の被災状況、今後の納品等の目処、確実な連絡手段、次回の連絡時期を報告する。 |
〔様式15〕主要顧客情報 |
|
●協力会社の被災状況把握 |
・協力会社に対して、事業所の被災状況、今後の納品の目処、確実な連絡手段、次回の連絡時期について報告を求める。 |
〔様式17-2〕主要供給者/業者情報[供給品目別] |
②中核事業の継続方針立案・体制確立
中核事業が受けたダメージを判断した上、中核事業の目標復旧時間等の継続方針を立案するとともに、それを実施するための体制を確立します。
|
中核事業の継続方針立案・体制確立 |
||
|
●中核事業のダメージ判断 |
・中核事業について、ボトルネックとなる事業資源の被災状況等から、中核事業が被ったダメージの大きさを把握する。 |
|
|
●目標復旧時間設定 |
・予め検討していた「目標復旧時間の目処」を元に、現在の被災状況、今後の事態進展の予測を考慮して設定する。 |
|
|
●応急・復旧対策方針の決定 |
・事業資源の損害が大きい場合、次のどの方針で目標復旧時間内に中核事業の復旧を目指すかを決定します(組み合わせもある)。 |
〔資料07〕災害事例における企業の事業継続・復旧シナリオ |
|
●財務の予測診断 |
・財務診断モデルを用いて、復旧費用、今後のキャッシュフロー、不足資金を予測する。 |
[5. 財務診断モデル] |
|
●実施体制の確立 |
・指揮命令系統と役割分担を従業員に明示する。 |
〔様式03〕BCPの策定・運用体制 |
|
●拠点場所の確保 |
・事業所が損傷した場合、顧客や協力会社と連絡が取れ、従業員を指揮できる拠点場所を確保する(自宅やプレハブ、自動車でも良い)。 |
〔様式08〕事業継続に係る各種資源の代替の情報 |



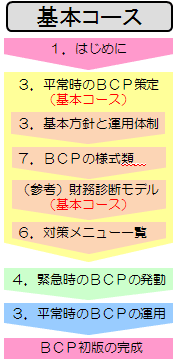
 公開にあたって
公開にあたって



