資料04 BCPの有無による緊急時対応シナリオ例
(3)建設業(地震災害)
|
|
BCP導入なし企業 |
BCP導入済み企業 |
|
想定 |
●小型ビル建設の下請け工務店(従業員10名+臨時作業員10名、社長は市内建設業組合の会長も務める)。 |
|
|
当日 |
●古い鉄筋コンクリート造の事務所は、柱にひびが入り、中で執務することは危険。 |
●(同左)事務所は、柱にひびが入り、中で執務することは危険。 |
|
数日間 |
●元請会社、孫請会社が社長に連絡を取ろうとするが、居場所が分らず、連絡が取れない。 |
●事務所敷地内のプレハブ倉庫を臨時の事業拠点とし、自家用発電機、備蓄の水と食料、連絡掲示板などを用意する。 |
|
数ヶ |
●その後も市役所等から災害復旧工事の引合いがあるが、手持現金がないため、臨時作業員を集めることが出来ず、受注できない。 |
●手持ち資金により、従業員と臨時作業員の月給、資材の支払いを行う。 |



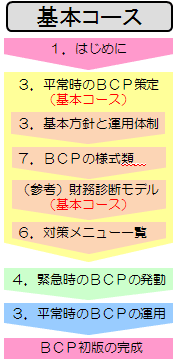
 公開にあたって
公開にあたって



